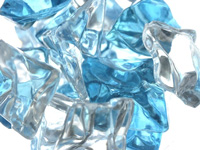* * *
戦闘後、各部署からの報告を一通り受けてからハーレイは青の間に足を向ける。
それをブルーに伝えるためだ。
最初の頃は思念波で終わらせていたが、ある時、思念波で済ませてしまったが為にブルーの負った傷に気づかなかったことがあった。
傷自体は大したことがなかったが、思念波では何があってもブルーに隠されてしまうと理解した。
あれほど強いサイオンを持っているのに、自分の身体の傷や不調に疎い。
いや、強いからこそカバーしてしまえるものと無意識に思っているのか、それとも認識しているのか。
いずれにせよそれを知ったハーレイは顔を見て報告すべきだと決め、その次の戦闘終了後、勇むような気持ちで青の間に行けば床は水浸しだった。
犯人を捜し歩けば、青の間の奥にあるプライベートエリアの端末の前にいた。
しっとり濡れた銀糸から水滴が滴り落ち、肩も背中も濡らしている。情け程度でも拭いたとは言えない状態で、バスローブどころかバスタオルさえ掛けておらず素肌を晒したままだった。
「ソルジャー!」
咎める意を強く込めて名を呼んだが、振り向きもせずに「調べたいことがあったから」と返してきた。
大股でクローゼットに向かい、バスタオルとバスローブを手にして問答無用で髪を拭き始める。
「揺らすな」
「ご自分に無頓着すぎます」
「急ぎだったから」
「それでもバスタオルかバスローブを羽織る時間は惜しむべきではありません。そうでないと―――」
「あ………」
キー入力が出来なくなってしまう。
「水濡れが原因でしょう」
指先から髪から、滴り落ちた水滴がキーボードを飾るように濡らしていた。
「………。調べたいことは終わったから」
大人しく髪を拭かれるに任せ、ブルーはバスローブに手を通した。
それが最初の日だった。
以来、報告に来る時間が早くても遅くても、ハーレイが戦闘の報告の為に足を踏み入れた時、青の間にブルーの姿を見ることはなかった。
いつもシャワーを浴びており、バスタオルとバスローブをハーレイに持ってこさせ、髪を拭かせている。
何故自分が?と疑問を持ちながらも、青の間が水浸しになることも、ブルーが体調を崩すことも歓迎出来ないハーレイは、毎回同じ事の繰り返しであっても職務と思いそれを行っているのだった。
* * *
今回も開け放たれているプライベートエリアのドアをくぐり、報告関連のメモリを小さなテーブルの上に置くと、バスタオルとバスローブを持ってハーレイはシャワールームへと足を向けた。
充分見計らったタイミングで出てきたブルーにバスローブを着せる。
そのままソファに座れば、背もたれに身体を預けてブルーはハーレイに向かって微笑した。
―――拭いて
―――そのつもりでタオルを持ってきたんだろう?
紅の瞳は悪戯な色彩を帯びてハーレイにそう語りかけている。
否と言うことも出来る。
無言でタオルをブルーに手渡してもいいだろう。
そうであっても恐らくブルーは文句の一つも言わない。
だが結果は見えていた。
ブルーが自分で拭くとは考えられない。
部屋のあちこちが濡れ、他の者をこの部屋に入れさせないとなれば、床を拭いて歩くのはハーレイの役目になる。
どちらを選択するか考える必要はなかった。
髪を拭き始めればブルーは目を閉じ、気持ちよさげにしている。
「………髪…」
ポソリとブルーが声を出す。
「髪、拭くの上手いな」
「トレーニングの機会が多いですから」
ブルーはクスリと笑い声を漏らしてから、
「僕のお陰だ」
悪びれず言ったブルーに、感情のない声で「そうですね」と答えた。
「本当に気持ちいい」
目を閉じたまま微笑すら浮かべてそう言われれば、悪い気はしない。
だが。
「拭くのが上手なら洗うのも上手だろうな」
「試してみたい、などど仰らないで下さい」
「何故だ?」
タオルから銀糸がすり抜け、ブルーは身を起こしてハーレイに尋ねる。向けられた視線は思いの外真剣で、ハーレイは答えに窮してしまった。
「言えない理由なのか」
「洗う方は下手です。恐らく」
「試したことはないんだろ?」
「………はい」
「理由は違うところにありそうだな」
ブルーに笑みが浮かぶ。
それはゾクリとする怖さを纏ったものだった。
追求されては困るとハーレイは違う話題を忙しく考え、
「今日は薔薇の香りですか?」
あからさまな話題転換にブルーの眉が歪んだが、座り直し、髪を再び拭くよう促す。
「手に取ったのがこれだった」
「生活に香りを、というスローガンを掲げて日夜研究しているようですが……そろそろ違う目標に変えさせた方がよろしいでしょうか」
「船内で育てている花、全ての香りを再生するまではと言っているようだな」
「はい。ようやく半分を過ぎたばかりです」
「今十六種類目。完成品を渡されて最初に使うのは嬉しいし楽しい」
「では最後まで?」
「そうだな。―――あぁそうだ。ハーレイはどんな香りが好きなんだ?」
「私は………」
好きな香りの名が口から出そうになり、慌てて止める。
「私は………薔薇が」
「花然とした香りが好みなのか。今度お前のところに薔薇のソープセットを届けるように言っておく」
「あ……いや…。私が薔薇の香りをさせていては……」
口籠もるハーレイを見やり、
「ブラウあたりに冷やかされそうだな」
「まず間違いないかと……」
「香りを楽しみたいだけか」
「はい」
「では、今、楽しんでいるんだな」
「えっ?」
ブルーの髪を拭く手が止まる。
「………そうです」
「そう。よかった」
「ソルジャーはどの香りがお好みです?」
「そうだな…」
真剣に考えている風に腕を組む。
「僕が好きなのは―――汗の匂いだな」
クルリと身を返してソファに膝立ちになり、驚いたハーレイの両肩に手を置いて肩口に顔を寄せると、
「お前の汗の匂い」
至近距離で視線を合わせればハーレイの心臓は憐れなほど激しく鼓動し、水を吸ったタオルを知らず握りしめていた。
「責務を果たした者の匂い」
ブルーの言葉を三度心の中で反芻して、ハーレイは自分の汗と特定したものではないと知ってホッとするはずだったが、胸の痛みを覚えてしまった。
それを気取られてしまったのか、ブルーの右手がハーレイの胸に移動し、ピッタリと手のひらをつけ、
「戦闘中、お前の心臓は不規則に鼓動したはずだ。恐怖と焦り、怒りと苦しみに浸されて。そう、今と同じように。今は何を恐れている?」
「………思い出した…だけです」
「何を?」
「……今日の戦闘です」
息苦しさを感じながらハーレイはタオルをソファの背にかけるとブルーの手を振り払うように移動し、携帯端末にメモリを挿入して今日の戦闘における各部署の報告をブルーに見せた。
「アルタミラで殲滅したはずのミュウが脱出したという噂は、軍内部では公然の秘密とされ始めたようです。もはや否定も噂の禁止もしておりません。寧ろその噂をもって士気を高めようとしています」
「明確な敵がいた方が操り易いからな」
不意にブルーから漏れ出た辛辣な言葉に、ハーレイは軽く目を見張った。
「今回、戦闘機に乗っていた人間の情報を得たか?」
「いえ。特別な人間だったのですか?」
「ああ。ある意味特別だ。囚人だからな」
ハーレイは今度こそ驚きに息が止まってしまった。
「一体……どういう……」
「軍は僕たちの存在を非公式ながら認めた。そして今まで極秘裏に生け捕るように命じていたが、極秘裏に抹殺せよという方針に転換した」
「………それと囚人と、どういう関係が?」
「ミュウを殺せ、ミュウの長を殺せ。殺した者は恩赦を与えると囁いた。軍人よりも必死になるだろう? そして物量に訴えてきた。ミュウの中で戦えるのは僕だけ。それは正しい選択だ」
「………」
「だが無駄だ」
ブルーは真っ直ぐハーレイを見つめ、
「僕をおとすつもりなら、ぬるい。どれ程の人数を揃えても目的は達し得ない」
「何故……です?」
「彼らは自分が生き残ろうとしているからだ。彼らの目的は僕じゃない、恩赦だ。中途半端な感情で僕を乱すことは出来ない。正気を失うほど強く思わなければ僕に触れることも不可能だ。そうだろう? ハーレイ」
ハーレイの手から端末が落ちる。
ブルーがサイオンで床への直撃を避けたが、それにハーレイは気づかなかった。
「………それは……」
呆然として呟く。
――― 正気を失うほど。
――― 強く、強く思えと……。
「……ソル…」
向けられた背中が名を呼ぶことを許さなかった。
ブルーはソファにかけられていたタオルを手にし、そっと口付ける。
その香を纏うに相応しい薔薇のような微笑を浮かべて振り返り、ブルーはタオルをハーレイの手に押しつけた。
「お前の好きな香りだろう? その香りに焦がれて正気を失ってみるといい」
言い終えるとブルーの姿はその場からかき消えた。
手の中のタオルからほのかに薔薇の香りが届く。
抱きしめて深く呼吸すれば、移り香に身も心も震えた。
抱擁 〜 ver.ハーレイ
了
BY AOI ARUTO
| Back |